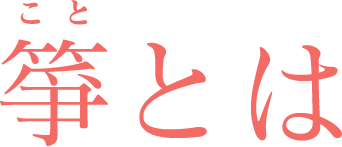箏は奈良時代に中国から伝わってきた楽器といわれています。
古くは宮中の音楽として発展し、歌舞伎音楽を経て、
やがて庶民的なお座敷音楽としても親しまれる身近な楽器になりました。
百人一首や源氏物語に登場する“貴族のお姫さまが弾く楽器”のような、
敷居の高いイメージがあるかもしれませんが、現代では決してそんなことはなく、
老若男女を問わずどなたでも気軽に楽しむことのできる楽器です。
- 年齢・性別問わずどなたでも気軽に始められます
- 無料体験・楽器レンタル可だから安心
- 古典曲からポップスまで幅広く習得できます
- 和の音色でストレス解消効果も期待できます
- 通常レッスン
-
1回1時間|
税込み5,500円※小学生以下は税込2,500円
- オンラインレッスン
-
1回1時間|
税込み4,500円※小学生以下は税込1,500円
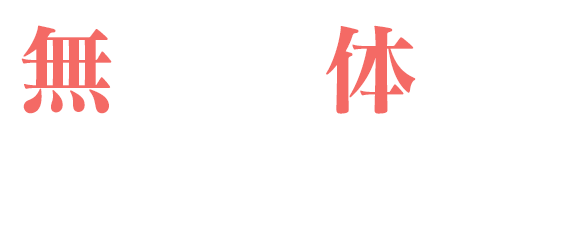
- 箏や三絃を弾くことが初めての方もご経験のある方も、まずは無料で体験していただけます。
一人が心細い方でも、お友達やご家族と一緒に体験していただけるので、どうぞ気軽にお問合せください。
-

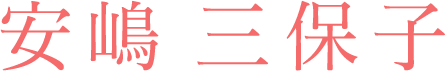
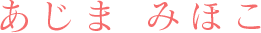
-
生田流箏曲(箏・三絃)演奏家。東京藝術大学邦楽科卒業、大学院修了。「伝統芸能プロジェクトチーム TRAD JAPAN」に所属。「賢順記念くるめ箏曲祭全国箏曲コンクール」はじめ、数々のコンクールで受賞歴を持つ。
現在は、生田流 箏・三絃教室にて講師業を行いながら、NHK Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」、NHK FM 邦楽百番などメディアへの出演、「サントリー“ROKU GIN”」のCM音楽や「藤間勘十郎 春秋座 名流舞踊公演」の舞台音楽の作曲、歌舞伎「風の谷のナウシカ」の劇中音楽の録音に参加するなど、作曲家・奏者としても活動中。